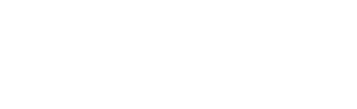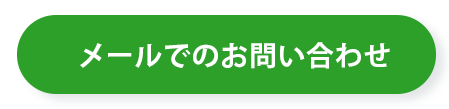OEM(受託製造)コラム
BLOG
子ども向けプロテイン製造で知っておくべき制限と注意点を解説

子ども向けプロテインは、不足しがちな栄養を補うアイテムとして需要が高まっており、商品数も増加しています。
子ども向けプロテインを製造する場合、大人向けプロテインとは異なる制限や注意点があります。
この記事では、成長期の子どもに適したタンパク質摂取量の設定や、敏感な味覚に合わせた味付けの工夫、飲みやすさを考えた形状の選択など、製造前に知っておくべき重要なポイントを解説します。
これから商品の製造を検討されている方はこの記事を参考にしてください。
SUNAO製薬では、サプリメントのOEMをお受けしております。製造をご計画中の方はお問い合わせください。
目次
子ども向けプロテインのニーズ

近年、子どもたちの食生活に少食や偏食の傾向が見られ、成長に必要な栄養を十分に摂取できていないのではないかと心配する保護者が増えています。
忙しい生活の中で毎日の食事だけで栄養バランスを整えることは難しく、不足しがちな栄養をサプリメントで補うことが一般的になってきました。
さらに、身体づくりやスポーツの成績向上を目的として、子どもにプロテインを取り入れる家庭も増加しています。
食事だけでは補いきれない栄養素を効率的に補給できる点や、運動や成長に必要なタンパク質を手軽に摂取できる点が、子ども向けプロテインのニーズを高めています。
子ども向けプロテインの配合量や注意点

子どもは成長段階にあるものの、大人ほど大量のたんぱく質を必要とするわけではありません。
そのため、摂取量は体重や年齢に応じて適切に調整することが大切です。処方を作る際は、必要量を超えて過剰摂取にならないよう注意する必要があります。
プロテインの配合量については、厚生労働省が公表する子どもの栄養摂取基準を参考に設定すると良いでしょう。
また、子ども向けの製品は食物アレルギーへの対応が必要不可欠です。
特定のアレルギー品目を含まない商品設計はもちろんのこと、製造過程におけるコンタミネーションを防ぐために、アレルギー対応が可能な工場を選定する必要があります。
しかし実際には、工場によっては離乳食や子ども向け商品のようにアレルギー基準が厳しく求められる製造を敬遠するケースも少なくありません。そのため、製造委託先を検討する際には注意が必要です。
子ども向けプロテインは、栄養が補給できるだけではなく、子どもが安心して口にできる安全性の確保が不可欠です。
栄養面と安全面の両立が、信頼される商品づくりにつながります。
子ども向けプロテインの味付けと工夫

子ども向けプロテインは、タンパク質などの栄養面での処方設計の他に味の工夫が非常に重要です。
子どもの味覚は大人よりも敏感で好みにこだわりのつよい子が多いため、味が気に入らないと継続して飲んでもらえません。
甘い風味は基本的に好まれる傾向にあるので、好みに合わせて甘いフレーバーで作る事が継続摂取の大きなポイントの1つとなります。
よく使われている味付けは、チョコレート、イチゴ、バニラなどが挙げられます。
粉末タイプは水や牛乳に溶かして飲む方法が一般的です。
甘味の付け方の1つに甘味料がありますが、甘味料は気にする保護者も多いため、使用の有無や種類には注意が必要です。
子どもに安心して続けてもらえるよう、味の設計とともに原料選びにも工夫が求められます。
使用者は子どもなので、続けてもらえる工夫は必須ですが、一方で購入者は保護者なので保護者が子供に飲ませたいと思う商品設計も必要になります。
こども向けプロテインの販売戦略

子ども向けプロテインの販売戦略について紹介します。大人向けの商品と大きく違う点は、使用者と購入者が違う点です。
子どもと大人(保護者)の両方の商品認知
子ども向けプロテインを販売する上で重要なのは、商品を実際に口にする「子ども」と、購入を決定する「保護者」の両方にアプローチすることです。
売上につなげるためには、双方の関心や価値観に応じた訴求を展開する必要があります。
子どもに対しては、「飲んでみたい」「おいしそう」と感じられるデザインや味わいがポイントとなります。
例えば、親しみやすいキャラクターをパッケージに取り入れる、甘さや風味を調整してジュース感覚で楽しめるようにするなど、「おやつ感覚」で手を伸ばしたくなる工夫が有効です。
保護者に対しては、「安心して子どもに与えられる」「成長や健康に役立つ」と信頼してもらえる情報提供が有効的です。
栄養価の説明や、専門家の推奨コメント、安全性への配慮を伝えることで、購買意欲を高める事ができます。
味を体感してもらう
子ども向けプロテインの販売は、「実際に飲んでみないと不安が拭えない」という課題があります。
子どもは味や食感に敏感なため、どれだけ栄養価や安全性を訴求しても、口に合わなければ継続的な利用にはつながりません。
そのため、まずは味を試す機会を提供することが大切です。
具体的には、少量入りのお試し商品やサンプル配布を用意することで、購入前の心理的なハードルを下げることができます。
一度子ども自身が「おいしい」「飲みやすい」と感じれば、その後の購入意欲は大きく高まり、本商品の購入につながりやすくなります。
さらに、継続利用を促すためには、定期購入プランの設計が効果的です。
初回お試し後にスムーズに本商品や定期コースへ誘導できる仕組みを用意すれば、長期的な顧客獲得につながります。
例えば「初回限定価格」「定期購入割引」「ポイント制度」などの特典を取り入れることで、保護者にとっても魅力的な選択肢となります。
よくある質問
- 子ども向けプロテインと大人向けプロテインの主な違いは何ですか?
- 成長段階の子どもは必要なたんぱく質量が大人より少なく、過剰摂取を避けるため配合量を年齢・体重に合わせて設計する必要があります。またアレルギー対応や味の工夫など、安全性と継続性を重視した処方が求められます。
- 甘味料を使うときに保護者が気にする点は?
- 合成甘味料の使用有無や安全性に関心が高いので、天然由来甘味料(ステビアなど)の採用や無添加設計を検討し、パッケージやWEBで明確に表示します。
- 子どもが飲みやすいプロテインの形状やタイプは?
- 水・牛乳に溶かしやすい微粉末タイプが一般的です。溶解スピードや食感テストを行い、ダマになりにくい処方にすることが重要です。
- 子どもと保護者それぞれに響く販売訴求のポイントは?
- 子どもにはキャラクター入りのパッケージや“おいしそう”なビジュアル、保護者には栄養価・品質管理・専門家コメントなど、両者の関心に合わせた情報設計が必要です。
まとめ

子ども向けプロテインの販売で注意するべき点は「使用者」と「購入者」が違う点です。
それぞれが重要視しているポイントも違う為、両方の関心を満たす商品作りが重要です。
子ども向けの商品はアレルギーの対応が必要不可欠となるので、製造先の工場がアレルギーに対してどの位対応が可能か製造前に必ず確認しましょう。
SUNAO製薬ではサプリメントのOEM製造をお受けしております。製造をご計画中の方はお問い合わせください。